This page contains no truth!
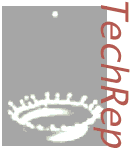 MOTHERプロジェクト
MOTHERプロジェクト
 大嘘百貨店へ戻る
大嘘百貨店へ戻る
8
0年代以降、先進各国が「小さな政府」をかかげ科学予算を削減してきた経緯もあってか、近年、夢のある大型科学プロジェクトがすっかりと消え失せてしまった。
そんな中、電総研が10年の歳月と7百億円の巨費を投じて推進する次世代コンピュータ計画「MOTHER」は、数少ない大型科学プロジェクトとして、今世界各国の注目を集めている。
「まさか、こんな形で子供のころの夢がかなうとは思いませんでしたよ」電総研西棟にあるMOTHERプロジェクト室を案内しながら、井口主幹研究員(49)は語る。「ほら、若いやつらも生き生きとしているでしょう」井口が指さす先では、20代の研究員たちがCADソフトを操り何かを設計している。
ここ第一実装課では、コンピュータの外部デザインを研究している。初期研究の段階でデザインの研究を行うこと自体きわめて異例だが、そこがMOTHERプロジェクトの「夢」の部分に他ならない。
「威圧感あふれるゴシック建築のような筐体、それから松本零士ゲージも欠かせませんね」第一実装課佐藤研究員(42)は語る。「何せ、私たちが作るのは凡百の計算機ではない。<マザーコンピュータ>なのですから」
M
OTHERプロジェクト、それはSFの世界にのみ存在するマザーコンピュータを実際に構築するプロジェクトである。プロジェクトの発足にあたっては、全国からマザーコンピュータ好きの優秀な研究者が集められた。「個人の思い入れがそれぞれ違うので、ベクトルの方向づけが難しいですね」井口が語るそばから、私の胸ポケットにある携帯が、間欠泉のようにスタッカート音を奏ではじめた。間髪を入れず、研究室の壁際にあるコーヒーメ−カーが蒸気を吹きはじめる。やがて、携帯とコーヒーメーカーの沸騰音は同期をとり、バッハのフーガを奏ではじめた。
「ああ、気にせんで下さい。インタフェース課の連中の悪戯ですよ」
佐藤がコーヒーポットを取り紙コップに注ぐと、急に携帯の音も鳴りやんだ。
「あそこ20代の人間が多いですから、サイバーパンクから入った奴が多いんですよ。で、こんな悪戯ばかりやってる」紙コップに入ったコーヒーを差し出すと、佐藤は肩をすくめてみせた。
「プロジェクト発足時のチュートリアルで、連中から『で、マザコンが発狂するとどうなるんですか?』と聞かれたんですよ。あ、マザコンというのはマザーコンピュータのことなんですが。『そりゃ、交差点の信号がランダムに点滅して車が渋滞になり、部下ロボットが一斉に反乱し・・』と説明すると奴ら笑うんですよ。美しくないとが芸がないとかいって」
井口が後を続ける。
「予算をにぎっている役所の連中もSF世代が多くなってきてますから、インタフェース課の連中がこういう悪戯すると、それはもう目を輝かせて喜びますよ。そういう意味では、渉外活動として有用なことは確かなんですが・・・」佐藤と井口は目を合わせ苦笑いを浮かべる「でも、私たちのような古い人間にとっては、深く目に見えず進行し、ある日突然あらわになる狂気こそが、マザーコンピュータの本質なんです」
別
室に移動し、マザーコンピュータ開発の歴史について伺うこととなった。「ああ、ありました、これですね」ロッカーの奥から、井口がベ−タ仕様のビデオテープを取り出してくる。デッキの再生ボタンを押すと、白衣を着た男たちが、軽自動車ほどもありそうな、複雑に配線が交錯する機械をいじっている画像がモニターに現れた。井口の説明では、MOTHERプロジェクトの前身となったHALプロジェクトの映像だそうだ。
「ここが視覚センサですね。14年前のことですから、テレビ撮影用の機材を流用してます。移動するだけでも一仕事で、肉体労働課なんて揶揄されてましたよ」
耳を澄ますと、ビデオの背景につっぱりHIGH SCHOOL ROCK'N ROLLが流れている。
「ごく初歩的なAIなんですけど、マザーコンピュータに相応しい基本アルゴリズムを組む段階で壁にぶちあたりましてね。プログラムではマザーコンピュータに必要な「らしさ」が出てこない。試行錯誤の結果、やはりこの種の「らしさ」には実地訓練が必要だということに気づきまして、HALに各種センサをつけて学習させることにしたのです」
佐藤がモニタ−を指さして説明する「あれが、HALの先生ですね。たしか翔とかなのってましたっけ」画面では、長ランにリーゼントの学生風の男数人が、煙草を吸いながらHALを囲んでいる。先生と呼ばれる翔がタバコをくわえ、HALをジロジロと眺める。HALはしばらくしてライターを先生に差し出すが、その緩慢な動作が先生の気に障ったのか、HALはローキックをみまわれている。
「この後、根性焼きをいれられるんですが....温度センサまではつけていなかったので、あまり効果はなかったようですね」
佐藤がデッキのパネルにあるボタンを押して、映像を早送りにする
「あの先生は今、回転寿司の板前をやっているはずですが...ああ、これ、HALが始めてカツ上げしたときの映像ですね」
「なめんなよ」なめ猫のステッカーを付けた黒ずくめのHALが、歌舞伎町をのし歩く。子分の肩に通りすがりの学生風の男が触れると、すかさずHALのマニピュレータ・アームが伸びて、男の胸ぐらを掴んだ。
「このときは、課の連中でシャンパンを開けて祝いましたよ。人間の手で、最も人間に近いコンピュータを生み出す、その始めの一歩を踏みだしたと。ですが...」
HALの筐体から無数のマニピュレータ・アームが伸び、男が悲鳴を上げたところでビデオが終わる。白黒のランダムドットがモニターを覆う。
「その後HALは姿を消しましてね。随分と探しました。しばらくは闇世界に身を投じて、パチンコの裏ROMなんか手掛けていたようですが..」声のトーンが下がる。
「ある日、パチンコのCPU能力が自分より高いことに気づき、富士の樹海に姿を消したんです」
遠い目をして語る佐藤は、まるでわが子を失った親のようだった。
M
OTHERプロジェクトの歴史に触れた私たちは、再び第一実装課へと戻った。
「HALの反省を踏まえて、我々は学習ブロックを外部化することにしたのです。本体が学習するのではなく、多くの「分身」が経験値を積み重ね、そのうち最良のものが”MOTHER”の主アルゴリズムとして採用されるのです」そういうと井口は、学習室と名付けられたドアをあけた。
ドアの向こうには、ずらりとモニターが並び、そのそれぞれが、異なった光景を映し出している。 「これがMOTHERの分身、学習ブロックの『まなぶくん』達です」
モニターの一つ、中学校の教室。授業を受ける生徒たちにまじって、自動車の衝突実験に登場するダミーのような人形が座っている。MOTHERのアルゴリズムは、この人形のセンサを通じて、静かな狂気を育んで行くのだ。
「優等生でソツなくこなす奴が突然キレる。今の中学生はまさに、我々が若いころにSF小説で接した、マザーコンピュータそのものです。これ以上の教師教師はいないでしょう」
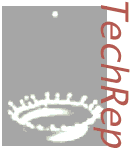 MOTHERプロジェクト
MOTHERプロジェクト
 大嘘百貨店へ戻る
大嘘百貨店へ戻る